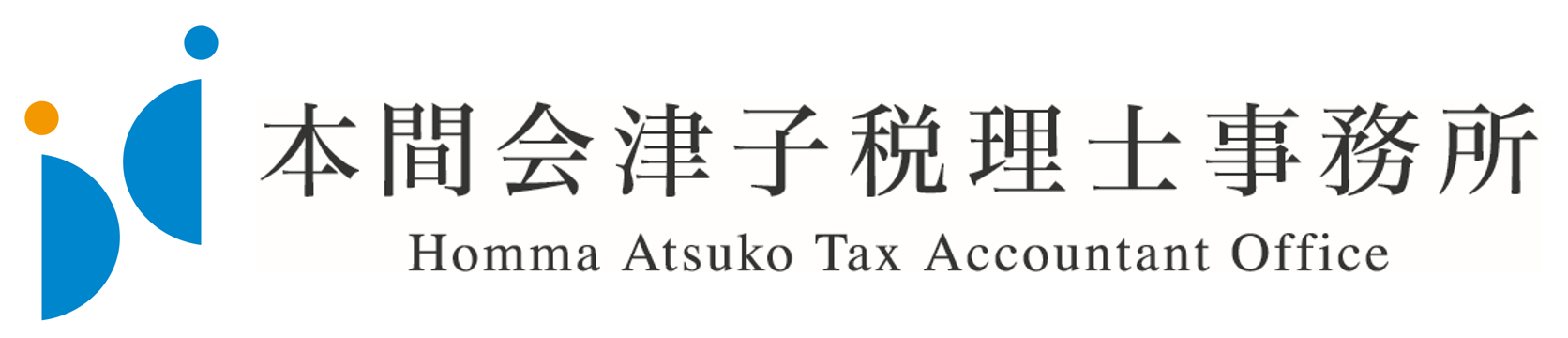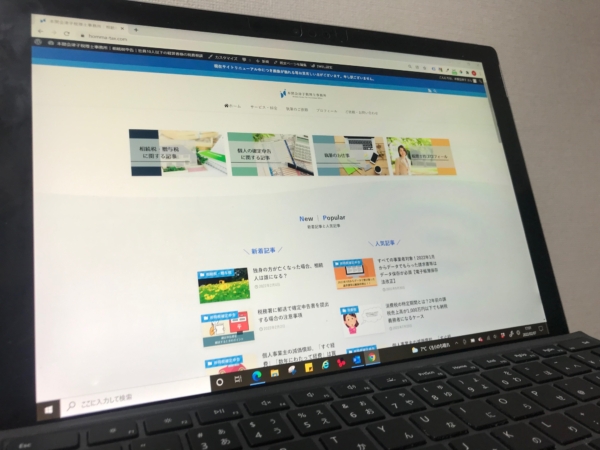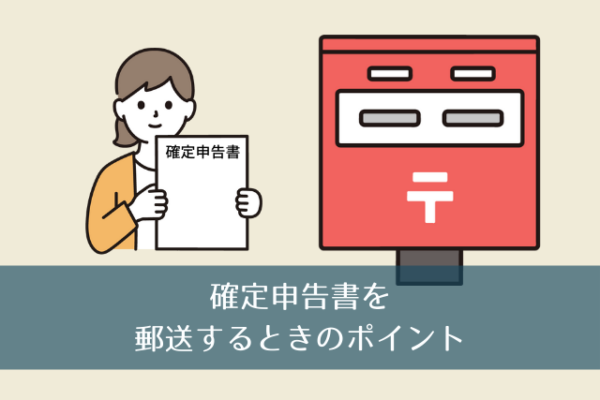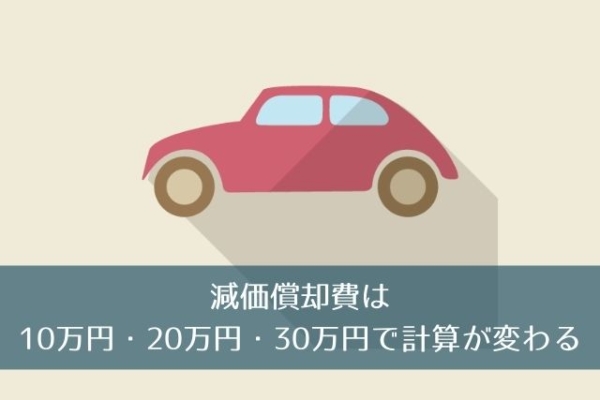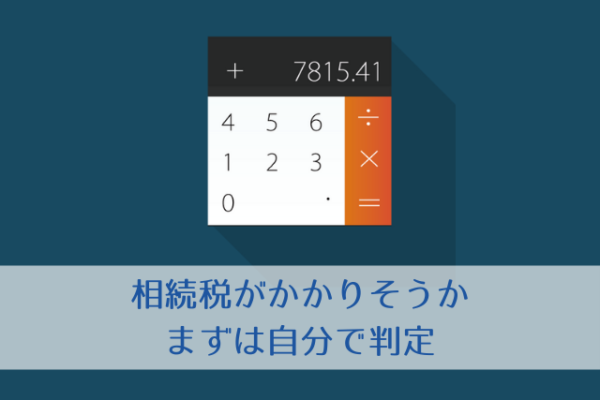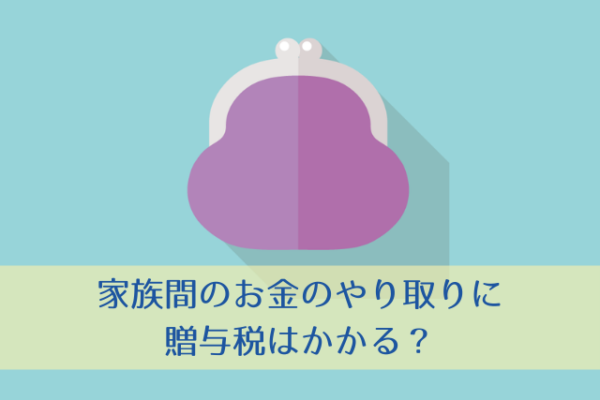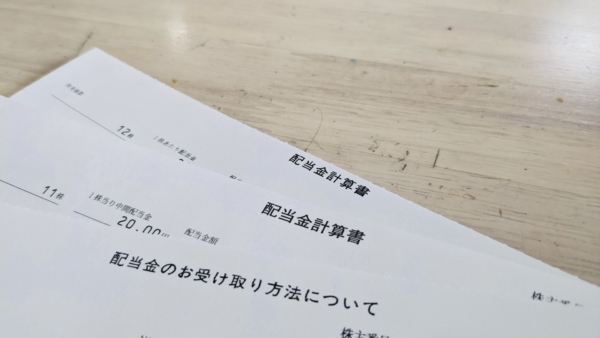税金の話– category –
-

ネットで確定申告の情報を調べるときに確認したいこと3つ
ネットで確定申告の調べ物をする際、税理士などの専門家が書いたブログを参考にされる方も多いでしょう。 ブログ記事は言葉をかみ砕いてやさしく書かれており、かつ実務で間違いやすい箇所などを反映しているため、国税庁ホームページに比べて大変わかりや... -

独身の方が亡くなった場合、相続人は誰になる?
2020年の国勢調査による生涯未婚率(50歳時未婚率)は男性25.7%(4人に1人)、女性16.4%(6人に1人)と過去最高を記録しました。 かく言う私もその一人となるでしょう。 独身の方が亡くなった場合、その財産はいったい誰が相続するのでしょうか? 配偶者... -

税務署に郵送で確定申告書を提出する場合の注意事項
「確定申告をするのは今年だけ」「今年から確定申告が必要になるが、今年はとりあえず紙で提出したい」などの理由で、郵送で確定申告書を提出する人も多いでしょう。 しかし、郵送により提出するにはいくつか注意事項があります。 郵送には決まりごとが多... -

個人事業主の減価償却。「すぐ経費」「数年にわたって経費」は買った金額で変わる
建物、車、パソコン、機械、デスクなど、長い期間にわたって事業に使う高額な資産は、買った年に全額経費にすることができず、使用できる期間にわたって少しずつ経費に計上します。 これを「減価償却」といいます。 買った資産を買った年にいくら経費にで... -

自宅兼事務所の場合、住宅ローン控除が受けられるのは原則居住用部分のみ
個人事業主(フリーランス)で、持ち家の一部を事務所として使っている人は多いでしょう。 その場合、事務所として使っている部分は減価償却費を経費とすることができます。 しかし住宅ローン控除を受けている場合、原則として事務所部分は住宅ローン控除... -

相続税がかかるかどうか自分でざっくり計算する方法【自宅+現金や株式という一般家庭向け】
今や亡くなった人100人中8人の割合で相続税がかかります。 特に都市部に持ち家がある人は、それだけで相続税の申告が必要な可能性が高いとされます。 相続税なんてお金持ちの税金だと思っていたけど、ひょっとしてウチもかかるのかしら? と不安に思うかも... -

家族間のお金のやり取りに贈与税はかかる?7つのパターンを紹介
家族間でお金のやり取りをすることはよくあるでしょう。 しかし中には、 あれっ?これって贈与税がかかる? と心配になることもあるかもしれません。 この記事では、 生活費 教育費 お祝い 保険金 親名義の家や車を使う 家族間の口座のお金の... -

相続人に未成年者がいる場合、安易に遺産分割協議ができないことに注意
人が亡くなる場合高齢であることが多いため、相続人に未成年者がいることはあまりありません。 しかし、 親が若くして亡くなってしまった。孫がおじいちゃんおばあちゃんの養子になっている。 というケースでは相続人に未成年者がいる場合があります。 遺... -

事業用と個人用の口座やクレジットカードが同じ場合の会計処理【事業主勘定】
事業用と個人用に分けていない口座やクレジットカードの仕訳はどうしたらいい? 個人事業主の場合、事業用と個人用に口座やクレジットカードをきっちり分けるに越したことはないのですが、どうしても両者が混在することもあるでしょう。 この記事では、 事... -

相続財産はどうやって探す?大きなヒントになるのは通帳と郵便物
人が亡くなると、その人が持っていた財産を相続人に引き継ぐ必要があります。 財産の額によっては相続税の申告の必要があるかもしれません。 しかし、亡くなった人が遺言書や財産目録、エンディングノートなど自分の財産がわかる資料を残しておらず、残さ... -

上場株式の配当所得で所得税は総合課税・住民税は申告不要とする手続きが令和3年の確定申告からラクに
上場株式の配当金には所得税と住民税がかかります。 上場株式の配当金の税金は天引きされ、確定申告をしなくてもOKです。 しかし課税所得が900万円以下の人であれば、あえて確定申告をすることで上場株式の配当金にかかる税金を減らすことができます。 上... -

電子取引のデータ保存義務化は2022年1月1日から2年間猶予【令和4年度税制改正大綱】
データでもらった請求書や領収書等は、2022年1月1日からデータで保存することが義務化される予定でした。 以前書いた記事が多くの方に読まれました。 しかし2022年税制改正大綱において、データ保存義務化が2年間猶予されることが明記されました。 電子取...